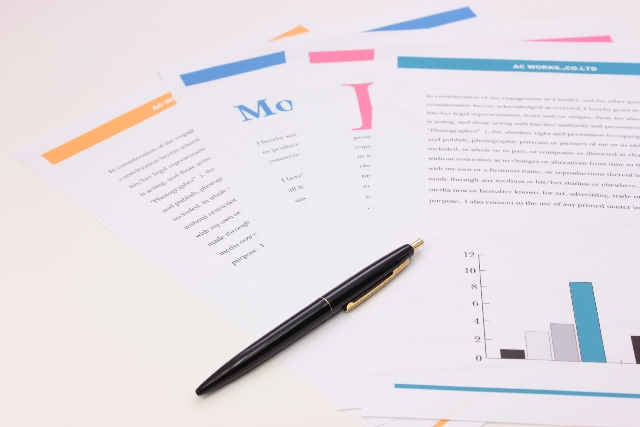


高年齢雇用継続給付金の給付要件に詳しい方にお聞きしたいのですが、現在61才です。この12月中旬まで60才で退職した会社にパートとして1年間働き一日5時間半で週に5日働き高年齢雇用継続給付金を
受けていました。しかし今年12月中旬に雇用終了となり退職しました。そして職をさがす中である会社が見つかり来年1月中旬に勤めることになりました。そこでは1日4時間の勤務、週5日勤務です。祝日は出勤です。ハローワークに聞いてみたところ、短時間労働なので高年齢雇用継続給付金を受ける可能性は微妙だというのです。では週5日労働の場合最低何時間働けば必ず受け取ることができるでしょうか。4時間半以上ならよいのでしょうか。会社にパートの時間の延長を申し出るのも躊躇してしまう気がします。給付金を受け取るには他に方法はありますか。よろしくお願いいたします。
受けていました。しかし今年12月中旬に雇用終了となり退職しました。そして職をさがす中である会社が見つかり来年1月中旬に勤めることになりました。そこでは1日4時間の勤務、週5日勤務です。祝日は出勤です。ハローワークに聞いてみたところ、短時間労働なので高年齢雇用継続給付金を受ける可能性は微妙だというのです。では週5日労働の場合最低何時間働けば必ず受け取ることができるでしょうか。4時間半以上ならよいのでしょうか。会社にパートの時間の延長を申し出るのも躊躇してしまう気がします。給付金を受け取るには他に方法はありますか。よろしくお願いいたします。
高年齢雇用継続給付を受給する要件の一つとして、被保険者資格を取得することです。1日4時間、週5日ですと、ちょうど20時間となります。雇用保険の被保険者となるには、週所定労働時間が20時間以上ですので、ハローワークの方は受給が微妙であると回答したと思われます。
CAD関連の仕事についての質問です。
現在、失業中です。以前は電気工事の仕事についておりました。
身体上の理由から退職しました。
具体的に書くと将来的に継続するのが難しいと判断した為です。
現在25歳でもうすぐ5歳になる娘と妻がおります。
今まで身体上の障害を理由に継続が困難になり何度か転職をしました。
自分自身、その度に妻に心配をかけてしまい。もうこれで終わりにしたい!!
そんな申し訳無い気持ちから、家族と話し合い将来的に続ける事が可能な仕事を模索しているなか
CADという言葉がでてきました。娘がいるので職業をより好みする気もなく継続できて家族の将来の為にと
CAD関連の仕事に就く為に失業手当をハローワークから貰い某学校でCADの勉強をする事を決意しました。
内容は3か月コース でAutoCADの2D,3D、機械製図、Inventorでの作図でした。
講座は終了したのですが、中々未経験を受け入れてくれる会社が無く頭を抱えています。
もう一つ前職の退職理由として身体上の理由をあげましたが具体的には、足に軽い障害があり退職と同時に
障害者手帳も今まで抵抗が強く、中々受け入れることができませんでしたがこれを機会に発行しました。
具合としましては、力仕事ができない程度、歩くのが遅い、それぐらいです。
経験不足と障害がネックになり就職活動が上手くいきません。
ハローワークにも求人があまりなく何件か面接させてもらいましたが駄目でした。
みなさんにこんな質問をぶつけてしまい申し訳ないと思いますが
正直どうしていいのかわからず天にもすがる思いで質問させてもらっています。
アドバイス頂ければ助かります。
現在、失業中です。以前は電気工事の仕事についておりました。
身体上の理由から退職しました。
具体的に書くと将来的に継続するのが難しいと判断した為です。
現在25歳でもうすぐ5歳になる娘と妻がおります。
今まで身体上の障害を理由に継続が困難になり何度か転職をしました。
自分自身、その度に妻に心配をかけてしまい。もうこれで終わりにしたい!!
そんな申し訳無い気持ちから、家族と話し合い将来的に続ける事が可能な仕事を模索しているなか
CADという言葉がでてきました。娘がいるので職業をより好みする気もなく継続できて家族の将来の為にと
CAD関連の仕事に就く為に失業手当をハローワークから貰い某学校でCADの勉強をする事を決意しました。
内容は3か月コース でAutoCADの2D,3D、機械製図、Inventorでの作図でした。
講座は終了したのですが、中々未経験を受け入れてくれる会社が無く頭を抱えています。
もう一つ前職の退職理由として身体上の理由をあげましたが具体的には、足に軽い障害があり退職と同時に
障害者手帳も今まで抵抗が強く、中々受け入れることができませんでしたがこれを機会に発行しました。
具合としましては、力仕事ができない程度、歩くのが遅い、それぐらいです。
経験不足と障害がネックになり就職活動が上手くいきません。
ハローワークにも求人があまりなく何件か面接させてもらいましたが駄目でした。
みなさんにこんな質問をぶつけてしまい申し訳ないと思いますが
正直どうしていいのかわからず天にもすがる思いで質問させてもらっています。
アドバイス頂ければ助かります。
おそらく、大多数の方が似たような誤解をされていると思います。
決して、あなたの今までの努力が無意味といっているのではないですが、
簡単にいいまして、「CADが使えます。」という言葉は、就職時もそれ以降の実務レベルでも意味を成しません。
遥か以前、20年くらい前。
まだ図面は手書きが主流だったころに、専門のオペレーターが必要だったときには、手書きの図面をトレースする仕事も
重要だった時代があります。
CADって、パソコンで図面を書くことでも、ソフトのことでもなく、「コンピュータの支援を受けながら設計をすること」です。
だから、「設計できます。」ということなら即戦力としての採用も考えられるが、
「CADが扱えます」という程度では、企業側にはあまりメリットがありません。
派遣でも、アルバイトでも何でもよいので「実務経験」を積んで、「設計」ができるようになりましょう。
はっきり言えば、設計ができるなら、CADが扱えようが、手書きしかできまいが、極端な話しなんでもよいのです。
設計者は図面が成果物です。その品質はパソコンを使ってもいいし、手書きでもよいのです。
ただ、実質、設計者がCADを使えないとしたら、それはそれで致命的なことだとは思います。
話しを整理しますと、「CADが扱えます。」ということにさしたる意味はなく、
「設計できる」ことがまず重要。設計が出来て、CADも扱えるのが普通。
で、さらにクライアントが感動する設計ができるなら、引く手あまた。
決して、あなたの今までの努力が無意味といっているのではないですが、
簡単にいいまして、「CADが使えます。」という言葉は、就職時もそれ以降の実務レベルでも意味を成しません。
遥か以前、20年くらい前。
まだ図面は手書きが主流だったころに、専門のオペレーターが必要だったときには、手書きの図面をトレースする仕事も
重要だった時代があります。
CADって、パソコンで図面を書くことでも、ソフトのことでもなく、「コンピュータの支援を受けながら設計をすること」です。
だから、「設計できます。」ということなら即戦力としての採用も考えられるが、
「CADが扱えます」という程度では、企業側にはあまりメリットがありません。
派遣でも、アルバイトでも何でもよいので「実務経験」を積んで、「設計」ができるようになりましょう。
はっきり言えば、設計ができるなら、CADが扱えようが、手書きしかできまいが、極端な話しなんでもよいのです。
設計者は図面が成果物です。その品質はパソコンを使ってもいいし、手書きでもよいのです。
ただ、実質、設計者がCADを使えないとしたら、それはそれで致命的なことだとは思います。
話しを整理しますと、「CADが扱えます。」ということにさしたる意味はなく、
「設計できる」ことがまず重要。設計が出来て、CADも扱えるのが普通。
で、さらにクライアントが感動する設計ができるなら、引く手あまた。
生活保護受給中に友人の車を借りて運転する事はOKですか?NGですか?
他の質問を見ましたが両方の答えがあり、実際どちらなのかと思いまして…
よろしくお願いします。
他の質問を見ましたが両方の答えがあり、実際どちらなのかと思いまして…
よろしくお願いします。
生保の人が友人の車を借りて運転する事はあると思いますよ。生保の人は車などの持つ余裕などありません「金銭的に」
友人であればなおさらに車を借りて、重いものなどを運ぶ事もあるでしょう。
生保の条文にどこにも車を借りてはいけないと言うものはありません。
又体が悪く生保を受けている人もいるでしょう。病院も少し遠くにあり借りる時もあるでしょう。
生保の人も生保を受けてない人も行動は同じです。運転にはみな気おつけるでしょう。
と言う事です。
就労の条文です。ハローワークに行くときもあるでしょう。その時に借りる場合もあります。「支出の節約」交通費等
(生活上の義務)
第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
友人であればなおさらに車を借りて、重いものなどを運ぶ事もあるでしょう。
生保の条文にどこにも車を借りてはいけないと言うものはありません。
又体が悪く生保を受けている人もいるでしょう。病院も少し遠くにあり借りる時もあるでしょう。
生保の人も生保を受けてない人も行動は同じです。運転にはみな気おつけるでしょう。
と言う事です。
就労の条文です。ハローワークに行くときもあるでしょう。その時に借りる場合もあります。「支出の節約」交通費等
(生活上の義務)
第六十条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。
関連する情報